チャップリンのコメディを特徴づけるのはその結末だ。最高傑作である『黄金狂時代』をのぞき、ハッピーエンドがない。
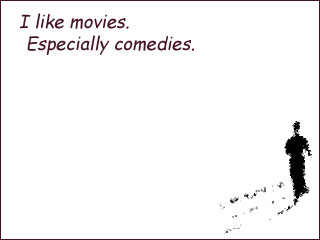
次くらいに有名な『モダン・タイムス』のラストは多少明るいが、そう感じるのは同伴者がいるからで、じっさいは絶望からの再出発というだけで、物質的には一文無しに等しい。あの道の先に幸せが待っているとはかぎらない。むしろ、それまで彼らを不幸にしていた問題はなにひとつ解決していない。
ボクが最も好きな『街の灯』のラストを「ハッピーエンドだと思ってた」という女性がいたが、あの有名な〈You?〉の字幕のあとに、幸せなんかありはしないのである。
『独裁者』は「あのあと、どうなったんだ?」とツッコまれるようなおわりであり、『殺人狂時代』はそもそもがブラック・コメディであるが、結末は死刑だ。
実質的な遺作と言われる『ライムライト』はコメディと呼ぶには重たく、ボクに言わせれば、コメディアンの出てくる悲劇で、ラストは舞台の片すみで、だれにも知られず、ひっそりと死んでいく。
主演作という意味で最後の長編である『ニューヨークの王様』は失敗作という評価が定着しているが、異国から追い出されてきた王様が少年ひとりを救い、自らは周囲になじめぬまま、再び去っていく。
そして、チャップリン映画のラストと言えば、『サーカス』でホレた娘の幸せを願う寂しい姿であり、中編『偽牧師』のどこにも属せずに一本道をペンギンのように歩いていく後ろ姿なのである。
これらが喜劇の王様と呼ばれた人の作品群であることをもういちど思い起こして欲しい。世に出回っている凡百のコメディ映画と比べてみて欲しい。タダゴトではないことがすぐにわかる。
だからといって、世間のつけたキャッチフレーズである〈笑いと涙の道化師〉みたいなことを言いたいわけではない。チャップリンの描いているのは、そんな安っぽいセンチメンタリズムとは無縁だ。それなのに、チャップリン映画をロクに見たこともない連中が〈笑いと涙の道化師〉という世評だけをたよりにチャップリンを否定していたりする。
素顔のチャップリンは生い立ち貧しく、人間ぎらいの守銭奴で権力を愛し、年若い娘の尻を追いまわす好色者であった。
チャップリン演じる主人公の行動原理は大半の作品において、空腹と女性への献身である(もしくは、生き延びること)。
そのストーリーをヒューマニズムととらえたりするのは、読みちがいもいいところで、演者であり、脚本家でもあるチャップリンのスケベさがにじみ出ているだけのことだ。
チャップリン映画に人類愛のようなものがある錯覚させる原因として大きいのは、『独裁者』のせい(それと『殺人狂時代』ラストの捨てゼリフ)だと思うが、あれは題材として国家を扱っているせいで、そう見えてしまうだけだ。
それまでの作品だと、浮浪者が警官に追われていたのが、ユダヤ人の床屋がナチスの親衛隊に追われるとなるだけで、大げさに受け取りたい観客が増える。
ボクの見方だと、あの作品の動機は個人的な怒りにもとづくものだと思う。ラストの民主主義擁護の演説も、個人の感想から出発し、個人へのメッセージとしておわっている。
ヒトラーやナチスが世界を席巻/蹂躙していくことに対する同時代的危機感も指摘されているが、そこもむしろ、あんな連中の台頭を許し、あるいは、熱狂している人々に対する危機感ではないだろうか。
チャップリン映画はハッキリとした悪役が出てことない。敵は貧困や貧しい人々に対して残酷な社会といった形を取る。もしくは、警官や個々の事情を省みず浮浪児を収監しようとする役人など体制の手先の形をとる。
つまり、その場では、ある人物が主人公をイジメているとしても、それはある層を代表する象徴的な存在に近い。悪人が出てくることはあるが、それもその場かぎりのストレスをあたえる存在で、すぐに退場する。ストーリーの解決部で倒すべき相手という意味での悪役ではない。
チャップリン映画で唯一、ハッキリした悪役と言っていいのが『独裁者』におけるヒトラーだ(これとて直接対決はなく、時代の象徴である意味合いが強いが、それはそれ)。
そのヒトラーを自分自身で、そっくりに、かつ、コッケイに演じるあたり、チャップリンのヘンタイ性が極立つ。これは諷刺よりなにより、おれにやらせてみろ的芸人魂のあらわれのように感じる。
チャップリン内部の創作過程で、どの部分が最初に動いたのかまでは知ることは不可能だが、いわゆる反戦映画のように作られたものではない。一人二役を活用したプロットじたいは中編『のらくら』の焼き直しだし、前半のギャグは中編時代の代表作『担え銃』の応用である。
オペラにおけるストーリーが歌を聞かせる口実であるのとおなじように、チャップリン映画のストーリーは彼のパントマイム芸やギャグを見せるための口実にすぎない。
ラストの演説は感動的だし、あれがチャップリンの心からのメッセージなのだとしても、作品にとっては飾りであるという点においては、『ライムライト』の説教くさい(が、ときに心に響く)名言と大差ない。
したがって、『独裁者』の〈あのあと〉は『担え銃』のラストと本質的には変わらないだろうと思う(あのままの形では長編のオチとして成立しないから、そうなっていないだけだ。チャップリン映画において、主人公の成功や地位の上昇は常にかりそめのものであり、やがて夢のように消える)。
『担え銃』のラストは、あの種のオチの代表例といってよく、ただ、無数にくり返された同種のオチがシラケる結果にしかならないのとちがって、ちゃんと笑えるようになっている。ボクの知るかぎりでは、唯一の成功例で、さすがと言うほかない。
チャップリンの映画を見るたび、うなるのは、フツーにおもしろい、笑えるという点である。同時代の他のコメディアンのコメディを見て、好ましく感じても、微笑むのがせいぜいである。
キートン、ロイドのクラスになると、さすがに笑ってしまうところもあるが、そういうシーンは1作品に1ヵ所あればいいところだ。
チャップリンだけがどうしてケタちがいなのか、というと、芸人としての能力の高さに加え、自ら監督し、その演出力が映画史上のトップクラスであるからだ。
すぐれた芸人のギャグを笑いのわかった名監督が適確なタイミングで撮るとなれば、笑えるに決まっている。
チャップリンは自らが出演しない『巴里の女性』というスレちがい悲劇を監督しており、この作品は艶笑喜劇の名手ルビッチをはじめ、サイレント映画の演出法に多大な影響をあたえた。
この『巴里の女性』は主演のエドナ・パーヴィアンスのために作られたと言われる。彼女はチャップリンと名コンビだった人で、中編第1作『犬の生活』のラストシーンの振る舞いがメチャクチャかわいい。
『犬の生活』はかろうじてハッピーエンドと言っていい作品だ。貧しくとも楽しい我が家的な小さな幸せを手に入れる。
かりに、主人公の立場に身をおいて、どの作品のラストが好ましいかと考えると、ボクの場合、『犬の生活』か『モダン・タイムス』を選ぶ。
シチュエーションの異なるこの2作品のラストシーンの印象がどこか似ているのは、〈2人でいれば大丈夫だぜ〉的な希望を感じるからだろう。
そりゃ、『黄金狂時代』のラストのような文句なしのハッピーエンドがいいに越したことはないが、どこか信用できないところがある。映画はあそこで〈エンド〉だが、人生はつづいていく。
『黄金狂時代』という作品はどんなにドタバタに大笑いしても、印象に残るのは、他人が楽しそうにしているのを窓の外からながめているシーンだ。〈小さなパンの踊り〉のシーンが美しいのも、それが芸として見事な上に、〈さみしい〉という感情を背景にしているからだ。
世にいるコメディ好きの人たちの中で、チャップリンの好きキライが分かれるのは、この点だと思う。そこに共感できるか、それとも、笑いになにかを上乗せするのは不純だと感じるか。
ボクは共感する。ただし、すでに述べた通り、ボクがチャップリンから受け取ったものと俗説の〈涙〉とは似て非なるものだ。世に出回ってる自称〈笑いと涙の人情喜劇〉の類で、いいと思ったものなど、ひとつもない。
チャップリン映画に、人情は無縁である。冷酷な社会にこづきまわされてる世の中の役に立っているとはあまり思えない男の話だ。その男が色や欲にかられて奮闘しても、そうしたスケベ心の大半は挫折する。
チャップリンが『モダン・タイムス』のために作った名曲「Smile」はそうした人間がおなじような目に合ってきた恋人に語りかける歌だ。巷で安易に口にされる「スマイル」とはちがう。
その2人がサバイバルする姿はコメディという形でたっぷりのギャグとともに表現される。だからこそ、あのほとんど絶望しかないラストシーンを観ても、
(自分もあんな風に恋人と歩き出せたらいいのになぁ)
と思うのだ。